これは大学時代のおはなし。
入院している患者さんの治療も終わり退院日を決めるとき。
もっと入院させて
症例
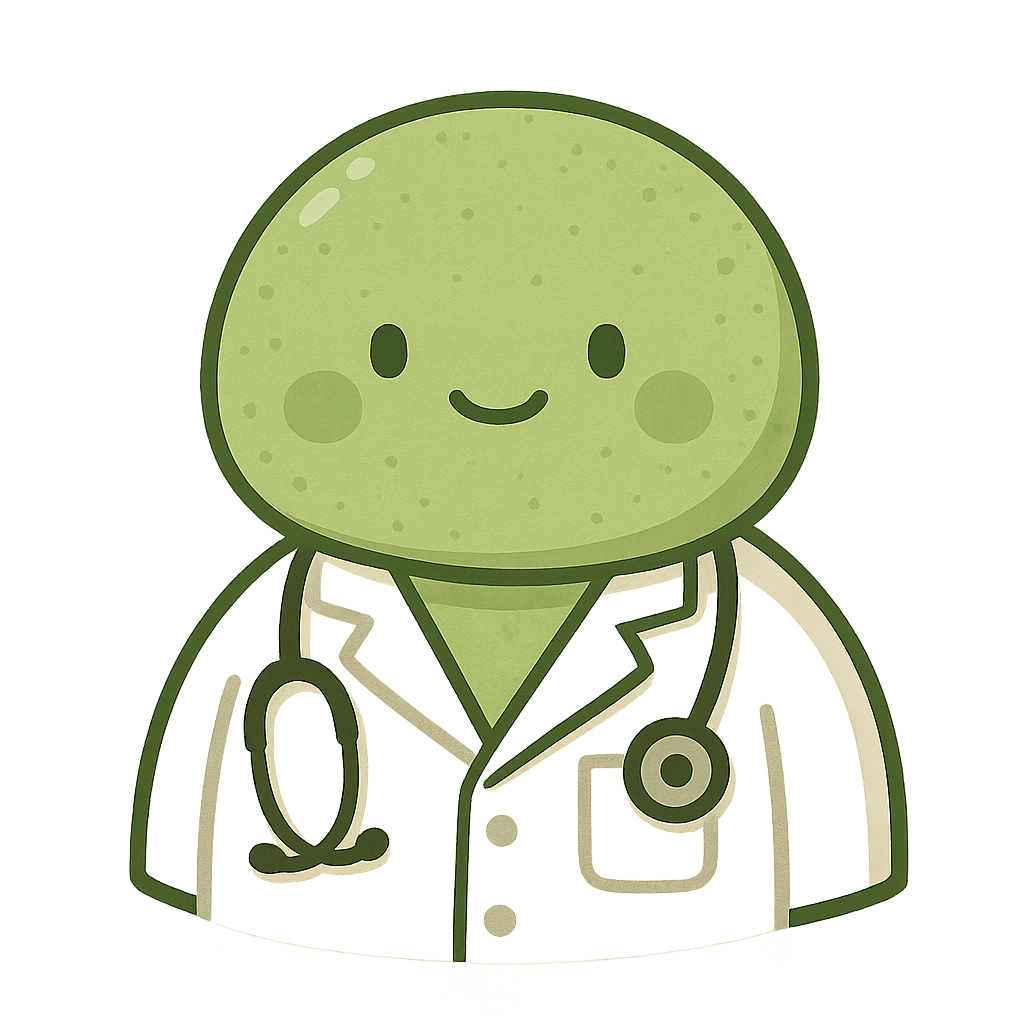
おはようございます。具合はいかがですか。

痛みも落ち着いて大分いいです。
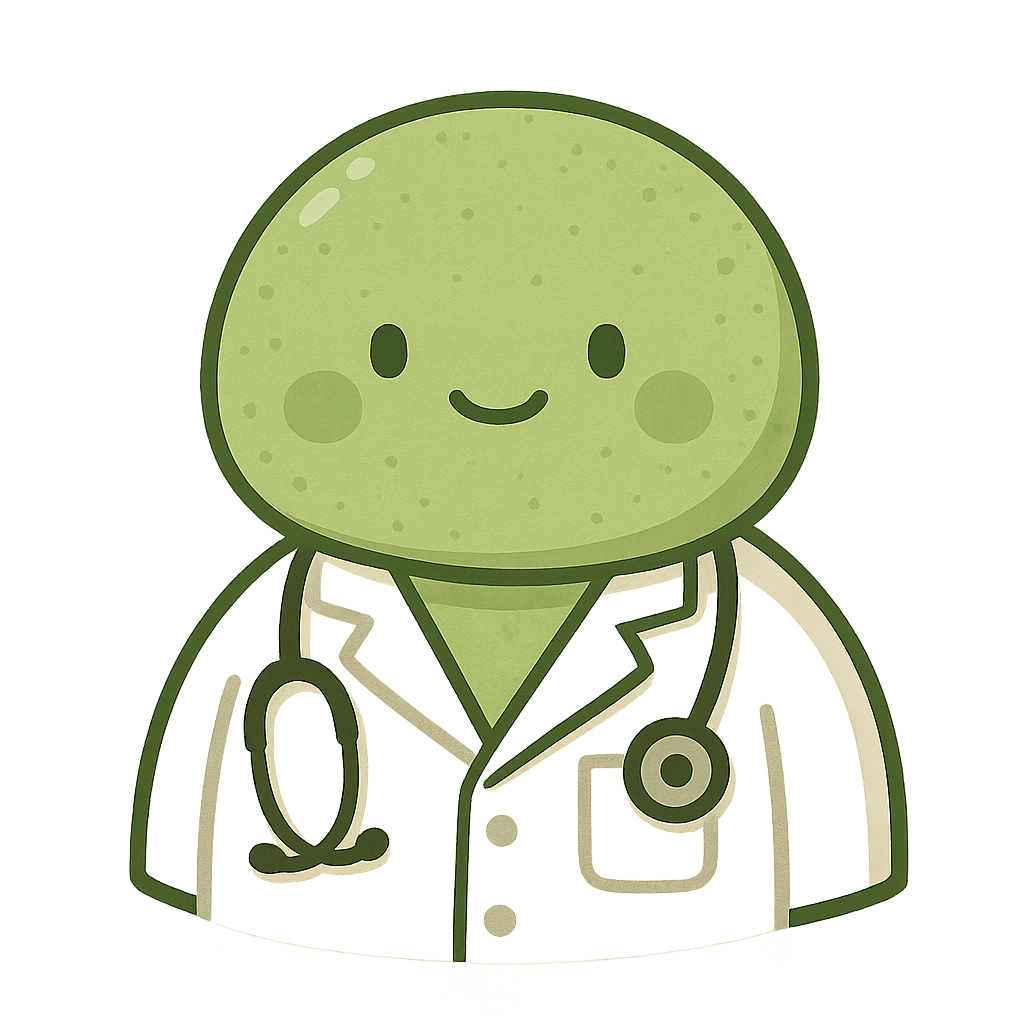
採血の具合もよいですし、そろそろ退院しましょう。

ん~、まだ心配なのでもう少し入院させてください
こういう方結構いらっしゃいます。
その理由はさまざまです。
- 家で一人だと不安
- 退院後の生活がうまくできるか自信がない
- 家族の都合が合わず、迎えに来られない
- 次の通院までが心配
- そもそも病院にいるほうが安心
珍しいところだとその日は仏滅で日取りが悪いからとかもあったりします。
以前の記事でも記載しておりますが
病院は”治す場所”、家は”回復する場所”なのです。
病院は治療をするための場所です。
症状が落ち着いたあとは、ご自宅での生活に戻ることが、回復にとってとても大切なのです。
入院生活はどうしても「受け身」になりがち。
自分で食事を用意したり、掃除・洗濯をしたりという日常の営みは、回復のプロセスそのものでもあります。
もちろん、不安が強くてどうしても自宅での生活に支障がある方は、
退院支援や訪問看護などの選択肢もご提案します。
ただ、「何となく不安」「漠然と心配」だからもう少しいたいという場合──
それは、少しずつ自分の足で歩き始めるタイミングかもしれません。
私たち医療者は、患者さんのその第一歩を応援したいと思っています。
中にはお金を払っているんだから入院継続の権利がある、
とおっしゃる方もおります。
医療資源には限りがあります。
病院のベッド、看護師の数、医師の手、検査や処方──
どれも無限にあるわけではありません。
退院できる状態の方が、なんとなくの不安だけでベッドを埋めてしまうと、
本当に緊急で治療が必要な方が入院できなくなることもあるのです。
もちろん、必要があれば入院継続は可能です。
ただ、医療は「権利」だけでなく、「優先度」と「必要性」によって判断されるものでもあります。
また長期入院が病院の収益になるかというと実は違います。
大病院ではDPC制度というものが導入されております。
DPC(Diagnosis Procedure Combination)とは、
病気の診断名と治療内容に基づいて、入院費が一律で決まる制度です。
つまり「入院日数や使った薬の量に関係なく、診断名ごとに決まった金額を病院が受け取る」という方式です。
たとえば胃潰瘍なら「〇日までが固定金額、それ以降は検査・治療をやった分だけ」というように、
長く入院すればするほど、病院側の収入は減っていく仕組みになっています。
DPCの存在は、病院が「本当に必要な治療を効率的に行う」ことを後押しする制度でもあります。
つまり、必要な治療を的確に、適切な期間で終えることが推奨されているのです。
解決策
- 外来通院や電話相談のフォローを活用する。
- 地域の訪問看護・訪問診療を利用する。
- 不安な症状があるなら正直に伝える。
外来通院や電話相談のフォローを活用する
退院後の不安が大きい方には、外来での早めの再診や電話でのフォローを行うことができます。
「困ったらすぐ来ていい」「電話で確認できる」という体制を知っているだけで、
不安はかなり軽減します。
地域の訪問看護・訪問診療を利用する
持病があって通院が大変な方、ひとり暮らしの高齢者には、
訪問看護や訪問診療の導入も選択肢になります。
また有事の際には近くのクリニックでとりあえず診察をうけ
判断してもらうために紹介状を記載させてもらうこともあります。
「病院でなくても見守ってもらえる安心」が得られます。
まとめ
早期退院は決して早く追い出したい、というわけではございません。
次の人が待っている、自宅での生活の方が私生活に早く復帰できるからになります。
また大病院の多くは赤字経営でありさらに資金難が続けば万が一閉院してしまう可能性もあります。
地域の中核病院である大病院が閉院してしまうと患者さんはさぞ困られるかと思います。
もし地域の中核病院が資金難で閉院してしまったら──
次に緊急で入院が必要になったとき、頼る場所がなくなってしまいます。
地域の皆さんが安心して暮らせる医療体制を維持するためにも、
「退院できるときに退院する」という当たり前の流れに、ご理解とご協力をいただければ幸いです。
それではお大事にどうぞ。
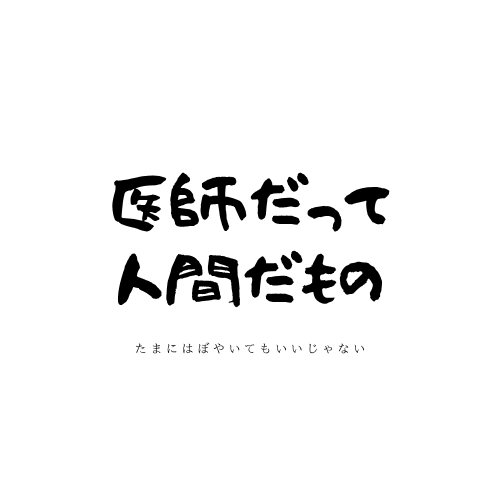

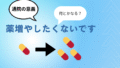

コメント