これはクリニック外来のときのこと
他院からの薬を確認した話
薬分からないの?
症例
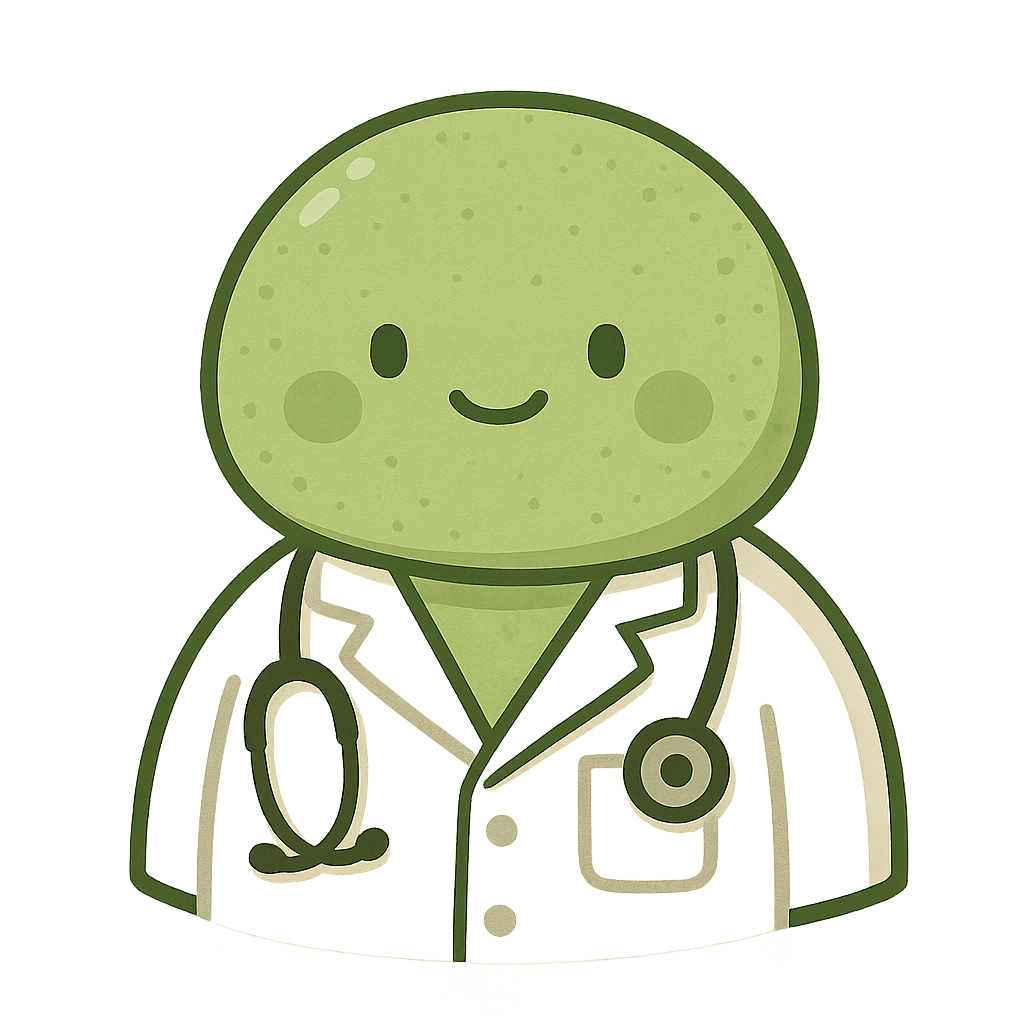
ではお薬をだしておきますね。どこかから別のお薬はもらっていますか?

〇〇病院から薬もらってます。
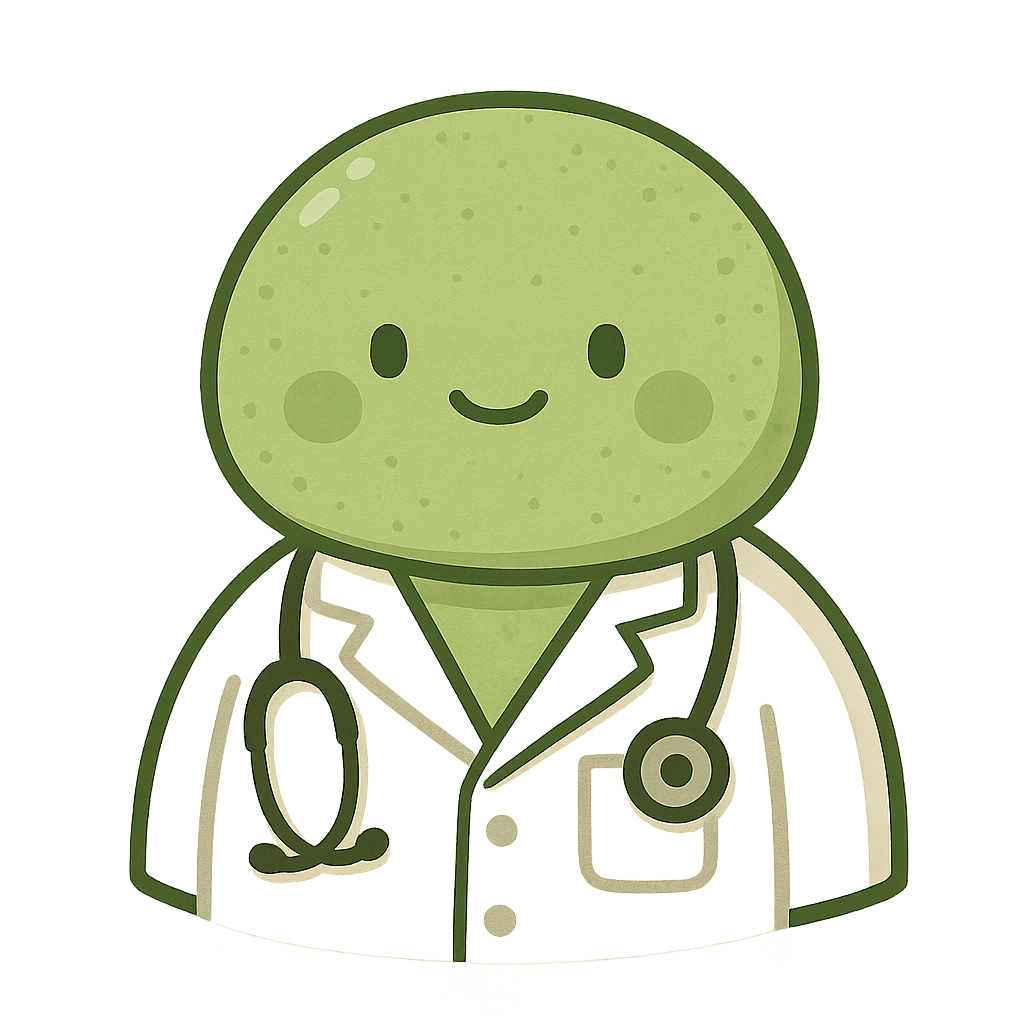
何を飲んでいますか?

×××××という薬です。
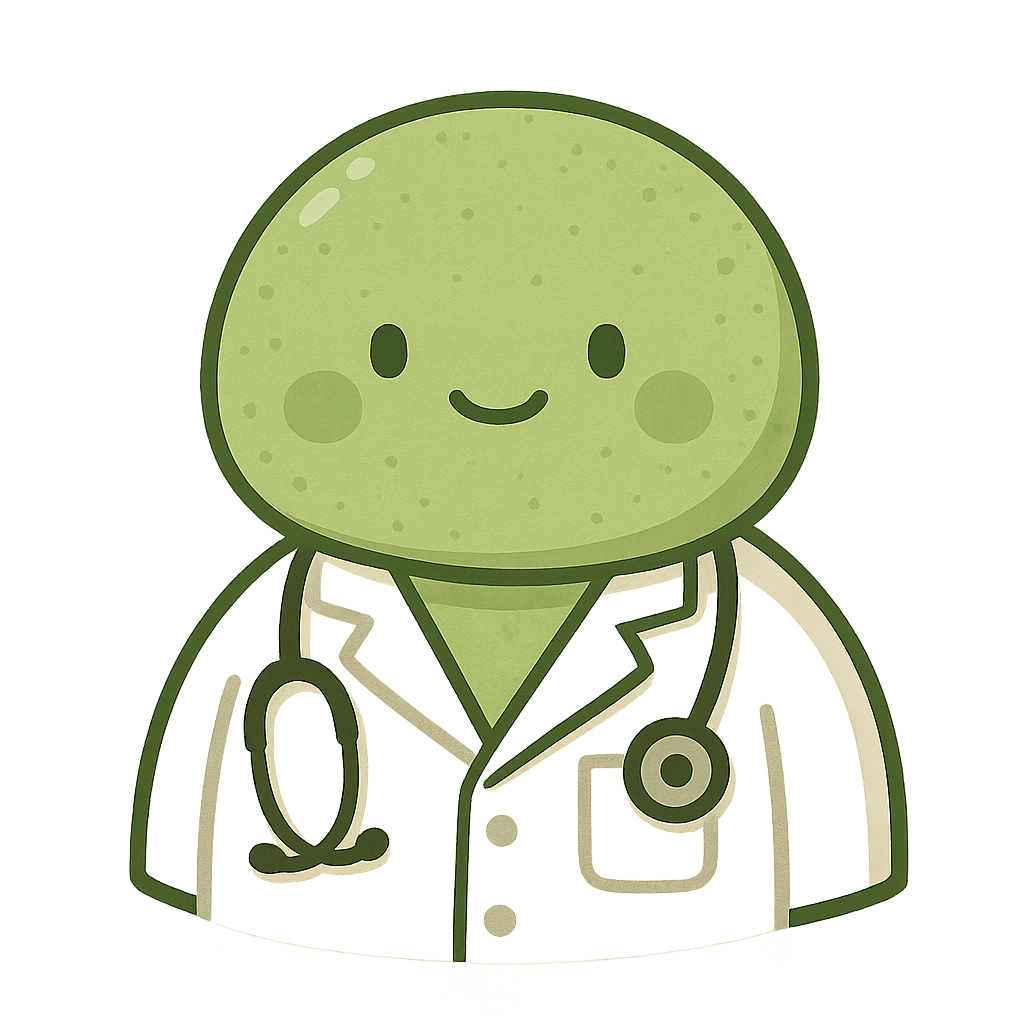
それはなんのお薬ですか?

え?薬分からないんですか?
とまでは言われないですが不信感をあらわにされることがあります。
正直に言います。
分かりません。
というと不勉強なように見られますが、薬全部わかるよなんて医者はいないかと思います。
医師によって差異はあるかと思いますが自分が使う頻度の高い薬しか分かりません。
私はもともとは消化器外科でしたので消化器関係の薬には明るいですし
クリニックでよく見る高血圧や糖尿などは勉強をしております。
しかし他の科精神科の薬などはあまり分かりません。
もちろん多くの薬を知っているということは医師としてのステータスにはなります。
薬が分からないのには以下の理由になります。
- 薬が多すぎる
- 新規薬剤、情報が更新されることもある
- 薬の情報がおおい
薬が多すぎる
別サイトの情報ですと2023年の時点で20000件程度あるようです。
こちらが薬剤情報が記載されている「今日の治療薬」
もう辞書です。総ページ数1440ページ。多いですね、長いですね、重いですね。
記載情報も全て大切なことです。覚えている人いるんですかね。
新規薬剤、情報が更新されることもある
薬剤会社の努力もあり、薬は毎年追加されております。
2024年で65品目が追加されました。
この中で自分が使う可能性がある薬剤はもちろんチェックは入れていますが
いきなり使い始めることはありません。
私の場合はある程度臨床(現場)での情報がそろってから使うことが多いです。
また薬剤自体は変わりませんが臨床で使用されたり研究されて適応が変更になることもあります。
最近ですと糖尿病の薬であったものが心不全でも使えるようになりました。
一般の方が考えるとなんで?となりそうですが機序を知っていると分かります。
あとはなんでかは分からないけどA疾患の薬だけど使ってたらB疾患に効く
適応はないけど効果はあるなど裏情報みたいなのもあります。
薬の情報がおおい
まずはこちらをご覧ください。
みんな大好きカロナール。
この一つの薬をとっても
総称名:カロナール
一般名:アセトアミノフェン
に加えて禁忌、用法容量、効能または効果、相互作用、注意事項、副作用・・・
などなどたくさん情報があります。
それを20000件。。。。無理です。
解決策
- 医師は薬の専門家ではない
- 医師が調べることを容認する
- 薬手帳を持参する
医師は薬の専門家ではない
医師は病気、治療の専門家になります。
薬の専門家は薬剤師になります。細かいことは薬剤師を頼るようにしてください。
医療も医師だけではなく分業してやっております。
医師が調べることを容認する
診察室で薬を調べることもあります。
上記の今日の治療薬や電子カルテ、携帯電話で調べることもあります。
こいつ分かってないな、みたいな冷たい眼を向けないでください。
患者さんのために調べているのです。
薬手帳を持参する
そもそも何の薬を飲んでいるか分からないという方も多いです。
薬ってカタカナの羅列でよく分からないですよね。
病院を受診する際には薬または薬手帳を持参していただけると助かります。
最近マイナンバーカードで処方を見ることはできますが情報が更新されるのには時間が必要になります。
なんだかんだでアナログが優秀です。
まとめ
薬の名前や作用を全部覚えている医師はいません。
でも「知らない薬を調べる」というのは、不安だからではなく、安全に診療するための当たり前の行動です。
医師・薬剤師・患者さん、それぞれの専門と役割を生かしてこそ医療は成り立ちます。
薬手帳や処方情報の共有は、その連携の第一歩。
お互いに「分からないことを確認するのは良いこと」と思える関係を作っていきたいですね。
それではお大事にどうぞ。
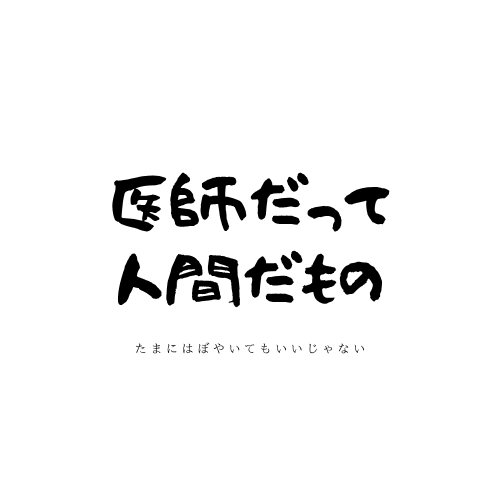
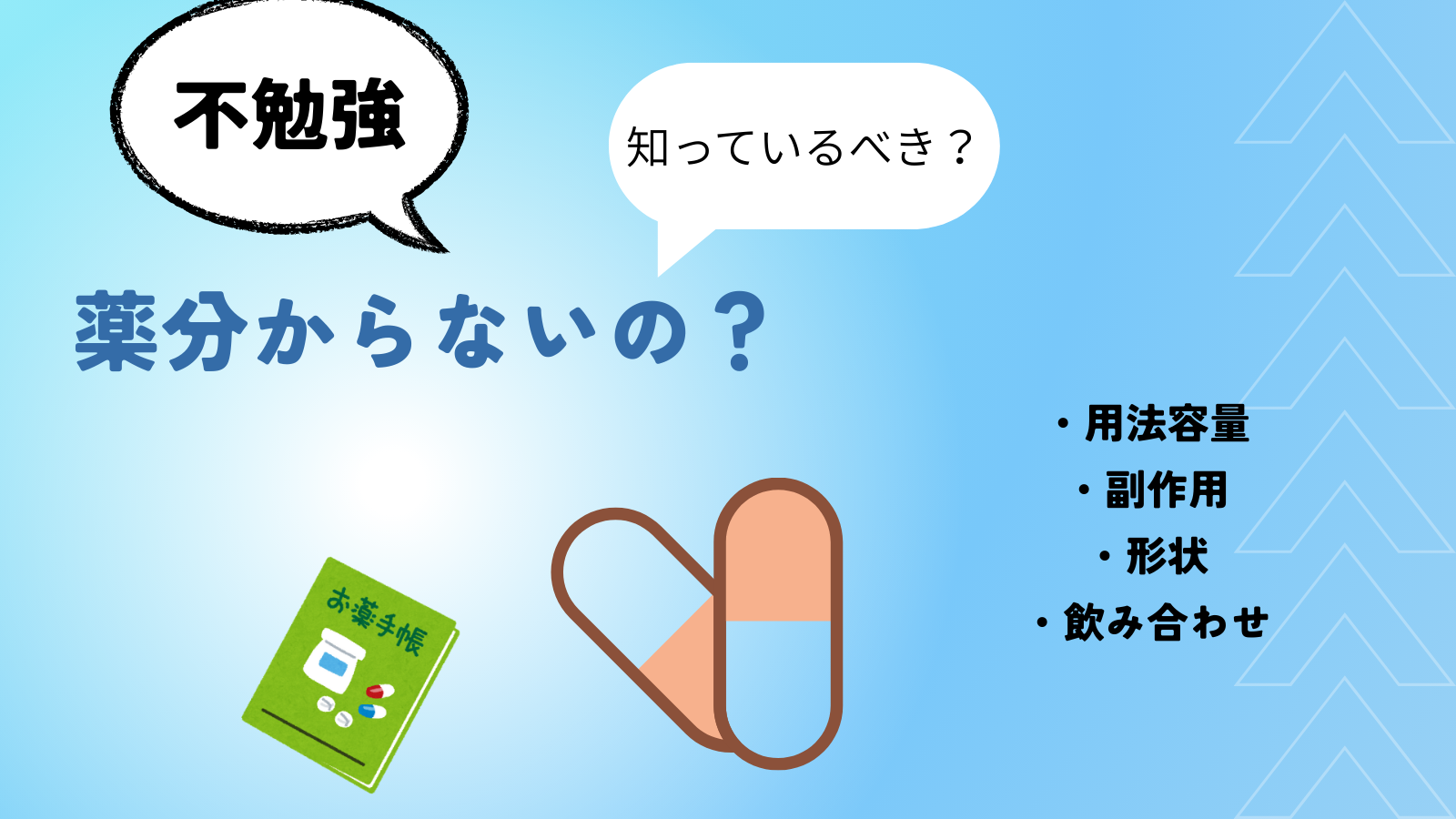
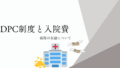
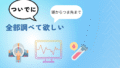
コメント